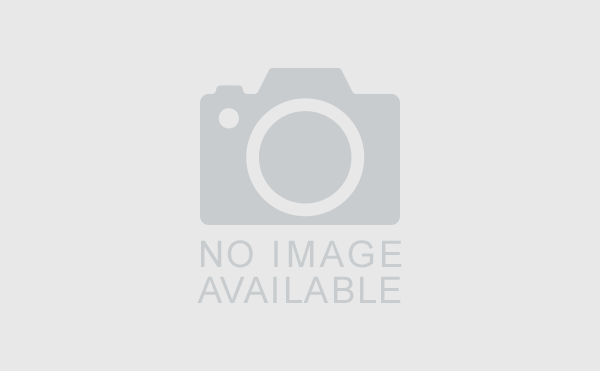27 エゾノリュウキンカ
キンポウゲ科の多年草。本州北部から北海道に分布します。低地から高山の渓流沿い、湿った草原や湿地などに群生します。足寄でも、川沿いのいたる所に大群落がありましたが、近年はシカの食害により大幅に少なくなりました。漢字で「蝦夷の立金花」と書き、直立した茎に金色の花を咲かせることからこの名が付きました。北海道では、谷地に生息し丸い葉がフキの葉に似ていることから「ヤチブキ」とも呼ばれています。茎の高さは五〇~七〇㎝で葉は丸く、5~6月にかけて黄色の花を咲かせます。一見、5~6枚の花びらがついてるように見えますが、実はこれは萼(がく)と呼ばれるもので花びらではありません。キンポウゲ科には毒のあるものが多く、猛毒で有名なトリカブトもこの仲間ですが、本種は茎、葉、花とも食用になり、古くから春の山菜としておひたしや和え物、天ぷらなどにして食べられます。ただし成長して大きくなったものは下痢などの中毒症状を起こすそうなのでご注意下さい。